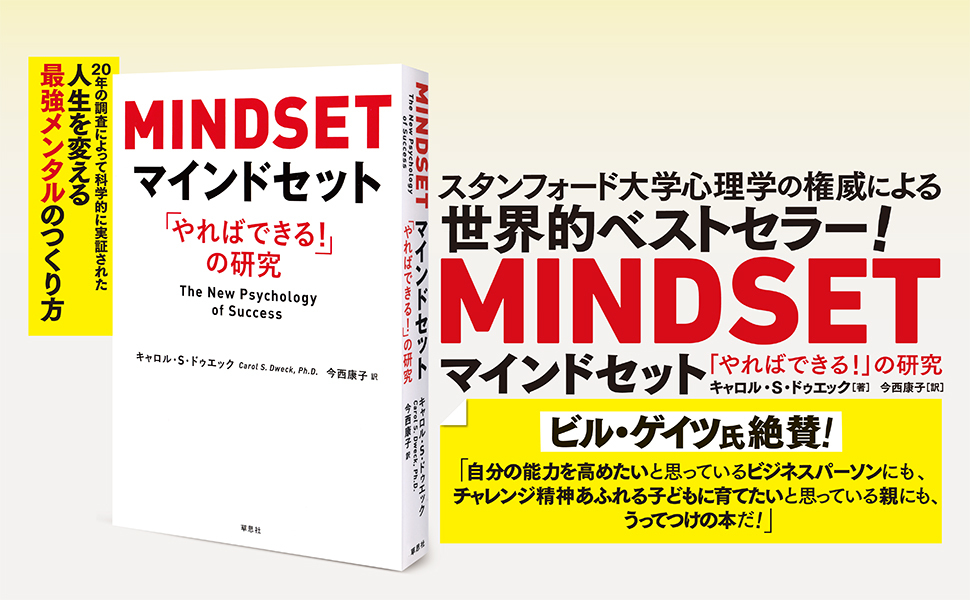10年近く前の書籍だが、内容が普遍であり度々メンタルが落ち込んだ時に読みなおす書籍を紹介したい。『マインドセット「やればできる! 」の研究』だ。レースが近づいてきたり、練習が思うようにいかなかったりしたとき、ふと読み返す一冊だ。
試合で思うような結果が出ない、練習で壁にぶつかっている…。そんな時、多くのアスリートが「自分には才能がないのかもしれない」「これが自分の限界なのか」と感じてしまうことがあるのではないだろうか。
しかし、そのように感じている「限界」は、実はあなたが無意識のうちに抱いている「思い込み」によって作られているのかもしれない。
スタンフォード大学の心理学者キャロル・S・ドゥエック博士はその著書『マインドセット「やればできる!」の研究』の中で、人の能力や成功に対する考え方、すなわち「マインドセット」が、個人の成長や達成に計り知れない影響を与えることを明らかにしている。
この本は、私たちの考え方一つで、人生が大きく変わる可能性を示唆しており 、アスリートが自らの潜在能力を最大限に引き出すための強力なヒントを与えてくれる。
この記事では、同書の内容を踏まえ、アスリートが勇気とモチベーションを高め、競技力を向上させるための「マインドセット」の重要性とその育成方法について解説する。
あなたのその「思い込み」が本当にあなたの限界なのか、それとも乗り越えられる壁なのか、一緒に探っていこう。
あなたはどっち?「固定マインドセット」と「成長マインドセット」
ドゥエック博士は、マインドセットには大きく分けて二つのタイプがあると提唱している。「固定マインドセット」と「成長マインドセット(しなやかマインドセット)」だ。
固定マインドセット
固定マインドセットを持つ人は、知能や才能といった能力は生まれつき決まっていて、努力しても変わらないと考える。彼らにとって重要なのは、自分の能力を証明し、他人から有能だと評価されることである。
そのため、失敗を極度に恐れる。なぜなら、失敗は自らの能力の欠如を決定的に示すものだと捉えるからだ。努力に対しても否定的で、「本当に才能があれば、努力など必要ない」と考えがちである。
スポーツの場面で言えば、固定マインドセットのアスリートは、大事な場面でミスをしたり、「自分はプレッシャーに弱い。勝負強さがないんだ」と結論づけ、次に同じような場面に出くわした場合、逃げるようになるかもしれない。
このような思考は、挑戦を避けさせ、成長の機会を自ら手放すことにつながる。失敗が自分の永続的な価値やアスリートとしてのアイデンティティを揺るがす脅威となるため、困難な課題から目を背けてしまうのだ。
成長マインドセット
一方、成長マインドセットを持つ人は、能力は努力や経験、学習によって伸ばすことができると信じている。彼らにとって重要なのは、学ぶこと、挑戦すること、そして成長することである。
失敗は恥ずべきことではなく、成長のための貴重なフィードバック(学習機会)だと捉える。努力こそが能力を高める道だと理解しているため、困難な課題にも積極的に取り組む。
同じくスポーツの場面で、成長マインドセットのアスリートがミスをした場合、「今回はうまくいかなかった。この経験から何を学べるだろう?この状況での練習をもっと積んで、プレッシャー下での技術を磨こう」と考える傾向にある。
彼らは結果よりも、そこから何を学び、次にどう活かすかという学習プロセスに焦点を当てる。
これらのマインドセットは、必ずしもどちらか一方に偏っているわけではなく、分野によって異なる場合もある。
しかし、どちらのマインドセットを主に持つかによって、アスリートとしての取り組み方、困難への対処、そして最終的な成長の度合いは大きく変わってくるのである。
固定マインドセットが結果による自己評価に終始しがちなのに対し、成長マインドセットは常に自己の向上を目指すため、長期的なキャリア形成において大きな差を生む可能性がある。
「成長マインドセット」がアスリートを強くする理由
では、なぜ「成長マインドセット」を持つことがアスリートをより強くするのだろうか。その理由は多岐にわたる。
まず、挑戦を恐れず、むしろ歓迎するようになる。
成長マインドセットを持つアスリートは、困難な課題や強敵との対戦、新しい技術の習得を、自らの能力を試し、成長させる絶好の機会と捉える。これにより、現状維持に甘んじることなく、常に新しい領域へ踏み出す勇気が生まれる。
次に、努力の価値を真に理解し、継続できる点である。
彼らは、才能だけでは限界があり、目標達成には質の高い努力が不可欠であると知っている。努力を「才能がない証」ではなく「成長の手段」と捉えるため、粘り強くトレーニングに励むことができる。
この自己向上の追求は、外部からの評価や報酬に左右されにくい内発的なモチベーションに繋がり、スポーツへの長期的な情熱を支える。
また、失敗や逆境から学び、力に変えることができる。
試合での敗北やミスは、能力不足の証明ではなく、改善点や新たな戦略を教えてくれる貴重な情報源となる。例えば、レース中に予期せぬ事態に苦しんだとしても、それをデータとして分析し、柔軟に対応策を練り直すことができる。
このような「失敗は学習機会」という捉え方は、精神的な落ち込みを最小限にし、迅速な立ち直りと適応を可能にする。
さらに、精神的な強さ、すなわちレジリエンス(精神的回復力)を高める。
困難な状況下でもストレス反応が低い傾向があるという研究報告もあり 、失望から立ち直り、スランプを乗り越え、モチベーションを維持する力は、成長マインドセットの大きな特徴である。
そして何より、継続的な成長ループを生み出す。
常に学び、成長することに焦点を当てているため、一時的な成功や失敗に一喜一憂せず、長期的な視点で自己のパフォーマンス向上を追求し続けることができる。
これは、過去の自分と比較し、自身の成長に注意を向ける「課題志向性」とも関連しており、自己肯定感を高めながら着実にステップアップしていく原動力となる。
チーム単位で見ても、個々人が成長マインドセットを持つことで、ミスに対する相互サポートが生まれ、建設的なフィードバックが交わされやすくなり、チーム全体の学習能力や結束力が高まることも期待できるだろう。
トップアスリートが実践する「成長マインドセット」の力
「成長マインドセット」は単なる理論ではない。世界のトップアスリートたちの多くが、その成功の要因として、このマインドセットを体現し、その重要性を語っている。
バスケットボールの神様と称されるマイケル・ジョーダンは、その代表例である。
高校時代に代表チームから落選した経験を持つなど、必ずしも最初から「天才」だったわけではなかった。
しかし、ドゥエック博士が「スポーツの歴史の中で最も努力家のアスリートだったかもしれない」と評するように 、絶え間ない努力と練習、そして失敗から学ぶ姿勢によって、伝説的な選手へと成長した。
「何本もシュートを外してきた。でも、挑戦することを恐れたことは一度もない」という言葉は、成長マインドセットの本質を捉えている。成功は、生まれ持った才能だけでなく、それを徹底的に磨き上げた結果であり、そのプロセスは多くの人に勇気を与える。
日本においても、ラグビー日本代表が「自分たちは体格で劣るから勝てない」という固定観念を捨て、「日本人にも強みがあり、それを伸ばせば勝てる」という成長マインドセットを持つことで歴史的な勝利を収めた例がある。
また、自転車競技の梶原悠未選手は、オリンピックの延期という予期せぬ事態に対し、「1年間あれば、さらに強くなって圧倒的な強さで勝負できる」と捉え直し、実際にメダルを獲得した。これもまた、逆境を成長の機会と捉える成長マインドセットの力強い現れである。
これらの事例は、トップレベルで活躍するためには、技術や体力だけでなく、「自分は成長できる」と信じ、困難に立ち向かい、努力を継続する心のあり方がいかに重要であるかを示している。
彼らの物語は、才能とは固定されたものではなく、努力と経験によって開花させることができるという希望を与え、他のアスリートや指導者たちにも心理的側面の重要性を認識させ、スポーツ界全体の成長を促す力を持っている。
今こそ「成長マインドセット」を鍛えよう
朗報なのは、成長マインドセットは生まれつきの性格ではなく、意識して鍛えることができるスキルだということである。
日々の小さな意識改革と行動の積み重ねが、あなたのマインドセットを少しずつ成長させていく。ここでは、アスリートが今日から実践できる具体的な方法をいくつか紹介する。
-
「できない」を「まだ、できない」に変える
何か新しいスキルや課題に直面し、「自分にはできない」と感じた時、その言葉の後に「まだ」を付け加えてみる。「この技術は、まだできない」「このタイムには、まだ届かない」というように。この小さな一言が、「今はできなくても、努力と学習を続ければいつかはできるようになる」という未来への可能性を心に灯す。この意識が、諦めずに挑戦を続ける原動力となるのである。
-
結果だけでなく「プロセス」と「努力」を認め、そこから学ぶ
試合の勝ち負けや記録達成といった結果だけに目を向けるのではなく、そこに至るまでのプロセスや努力、そしてそこから得られた学びに焦点を当てよう。たとえ望む結果が得られなくても、「今回の挑戦で何を学べただろうか?」「どの部分が以前より成長しただろうか?」と自問し、自分の取り組みを肯定的に評価することが重要である。この習慣が、結果に左右されない安定したモチベーションと、次への具体的な改善点を見つける洞察力を養う。
-
失敗を「成長の糧」と捉え、挑戦を恐れない
失敗は、あなたの能力が低いことの証明ではない。それは、目標達成のために何が不足していて、何を改善すべきかを教えてくれる貴重なフィードバックである。ミスをしたら、「このミスから何を学べるか?」と問いかけ、具体的な対策を考えよう。そして、失敗を恐れずに新しいことや困難な課題に積極的に挑戦することだ。挑戦と失敗の経験を積むことで、失敗に対する耐性がつき、それを成長の機会として活かせるようになる。
これらの小さな実践を続けることで、思考の癖が徐々に変わり、行動が変化し、それがまた小さな成功体験に繋がり、さらに成長マインドセットが強化されるという好循環が生まれる。
また、指導者や保護者といった周囲の大人たちが、結果だけでなく努力や挑戦の過程を認め、失敗から学ぶ姿勢を具体的に示すことも、アスリートの成長マインドセット育成には不可欠である。
まとめ:「やればできる!」その信念が未来を拓く
キャロル・S・ドゥエック博士の著書『マインドセット「やればできる!」の研究』が示すように、私たちのマインドセットこそが、自らの可能性の扉を開く鍵なのである。
固定マインドセットに縛られれば、才能という名の檻の中で自分の限界を早々に定めてしまうかもしれない。しかし、成長マインドセットを手にすれば、努力と学習を通じて、その限界をどこまでも押し広げていくことができる。
成長マインドセットを持つということは、困難が存在しないかのように振る舞ったり、失敗の痛手を感じないようにしたりすることではない。重要なのは、それらに直面したときに、どう反応するかである。
挑戦から逃げるのではなく学びの機会と捉え、失敗に打ちひしがれるのではなく次への糧とする。その前向きな姿勢こそが、成長マインドセットの本質なのだ。
マイケル・ジョーダンはこう語っている。「何かを達成する前に、まず自分自身にそれを期待しなくてはならない」と。
才能はあくまで出発点に過ぎない。今日この瞬間から「成長マインドセット」を意識し、日々の努力を積み重ね、挑戦を恐れず、自分自身のまだ見ぬ可能性を信じて突き進んでほしい。
「やればできる!」という信念は、単なる楽観論ではなく、努力と学びによって能力を高められるという自己への信頼である。その力強い信念が、あなたの競技人生を、そして競技を離れた後の人生をも 、豊かに、そして力強く切り拓いていくことだろう。